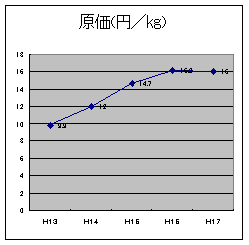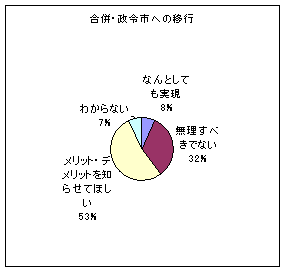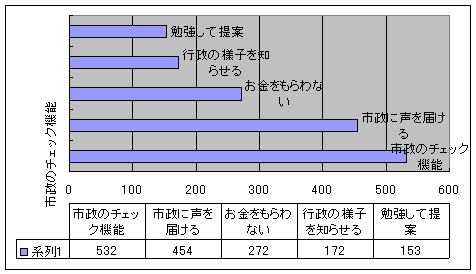���S���y�����A���炵���������鐭�����I
���{���Y�}�s�c�c�̒�Ăɂ��A5080�l�Ɂw��Q�ҍT���F�菑�x����t����܂���
�@�ŋ��̐\���͍ς܂���܂������H
�F�{�s�́A�v���F��P�`�T�܂ł̕���ΏۂɁA06�N�x����u��Q�ҍT���Ώێҁv�Ƃ��ĔF�肷�鐧�x��������܂����B
�@1��5562�l�ɐ\�����𑗕t�����Ƃ���A5342�l�̐\��������A���ʏ�Q�҂�2773�l�A��Q�҂�2307�l���F�肳��܂����B
�@��Q�Ҏ蒠���Q�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�����ł�Z���ł̏�Q�ҍT���̑ΏۂƂȂ�܂��B�{�l����ېł̏ꍇ�ł��A����҂�}�{���Ă�����́A���ʏ�Q�ғ������Z ���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�����̂��ꂳ�V�l�ی��{�ݓ�������Ă���`����A�u�w���ʏ�Q�ҁx�ɔF�肳��A���ʏ�Q�ҍT���i40���~�j�Ɠ������Z�i35���~�j���邱�� ���o���܂����v�ƕ�����܂����B
������ł��Ԃɍ����܂��B�����k��������!
�����ŁE�Z���ł̕��S�y�����ł���Ƌ��ɁA�A�����A���ی�������@�E������p�i�H��j���y���ł���ꍇ������܂��B
�v���F����Ă����Ȃ��ꍇ���A�T���F��ΏۂƂȂ�ꍇ������܂��B�i�₢���킹��F����ی�������TEL�R�Q�W�`�Q�R�P�P�j
�����̏ꍇ�́A�X�ɍT���������܂��B�ڂ����͎s���ʼnۂցB�@�@TEL�@�R�Q�W�`�Q�P�W�P
07�N�x�������E�����̒藦���� �p�~�ȂǂŖ�14���~�̕��S���I
| �������� | �e���l�� | �e���z�i�S���~�j | ���� |
| �藦���ł̔p�~ | ��@275,000�l | ��@1,334 | �[�Ŏ҂̖�92.9�� |
| 65�Δ�ېŌ��x�z�̔p�~ | ��@�@11,800�l | ��@�@�@12 | 65�Έȏ�̖�9.6�� |
| ���v����Ȃ̔�ېő[�u�̔p�~ | ��@�@42,000�l | ��@�@�@�@7 | �[�Ŏ҂̖�14.2�� |
| �V�N�ҍT���̔p�~ | ��@�@23,000�l | ��@�@�@36 | �[�Ŏ҂̖�7.8�� |
| ���I�N���T���ɌW��Œ�ۏ�z�̈������� | ��@�@23,000�l | ��@�@�@14 | �[�Ŏ҂̖�7.8�� |
| �v | ��@�@14���~ |
�y�������̕��ʎ��W�z����L�ȊO�ɂ��A65�Έȏ�̕��ɂ́A���ی����E���ۗ��̈����グ���\�肳��Ă��܂��B�i�N���T���̏k���ɂ����́j
20�N�ԁA3��5000���~���̐��ӌ_��𑱂��Ă����u���������Ď��������i���Ɓv
2���Ǝ҂����Ƃ�Ɛ肵�Ă������ӌ_�����߁A���������W�E�I�ʎ��Ǝ҂̌��S�Ȉ琬���I
����ʂ͌��E�ϑ���͑��A1�l��������Ă��Ȃ��Ԃ�2�l���̈ϑ���
| �N�x | �g�P�R | �g�P�S | �g�P�T | �g�P�U | �g�P�V |
| �������(��) | 34,401 | 29,351 | 24,425 | 22,316 | 22,368 |
| �ϑ���(��~ | 340,011 | 351,444 | 359,641 | 361,731 | 358,533 |
| ����(�~�^�s) | �X�D�X | �P�Q | �P�S�D�V | �P�U�D�Q | �P�U |
| ���p�v(��~) | 75,225 | 88,779 | 101,529 | 90,519 | 104,846 |
�@����ʂ�5�N�ԂłR�T���������Ă���̂ɁA�ϑ���͋t�ɑ����Ă��܂��B�����āA���W������p�̒P����1.6�{�ɑ����Ă��܂��B
���̂悤�Ȏ��W�E�I�ʂ̎��Ƃ̏ꍇ�A��ʓI�ɂ́A����ʂɈϑ���͔�Ⴕ�܂��B����ł́A�ϑ�������m�ۂ��邽�߂ɁA���ʎ��W�����������グ���Ă��� �悤�Ȃ��̂ł��B
�@�s��������d�l���ɂ͎Ԃ̑䐔��z�u�l������߂��Ȃ��܂܁A�ϑ����9��̉���ԗ���2��������Ԃ����v�Z�ŁA�ώZ����Ă��܂��B
���ۂɂ́A1���1������Ԃ��č�Ƃ��s���Ă��邽�߁A���ۂ������Ă����p���������ϑ�������Ă��܂��B
�@�܂��A���p�v���������Ă���o��ɂ��Ă��s�͔c�����Ă��炸�A���p�v��Ⴍ����A�s����Ƃ���ϑ���͂���ɑ�����v�Z�ɂȂ�܂��B
�@���̂悤�Ȍ_��20�N�ɂ��킽��A�����2���Ǝ҂ɐ��ӌ_��ňϑ�����Ă��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�������Ď��������i���Ƃւ̑����̎��Ǝ҂̎Q�������T�C�N���Љ�̒S����ƂȂ��Ƃ̈琬�ɁI
�@�Q�O�N���̒����ɂ킽�鐏�ӌ_��ɂ���āA�Q�̎��Ǝ҂��d����Ɛ肵�Ă��邽�߂ɁA�������̎��W�E�I�ʂ͌����ē�����Ƃł͂Ȃ��ɂ�������炸�A�� ����ł���Ǝ҂�����Ă��܂���B
�@���N�A���Q��ł������ӌ_����������A���W�ƑI�ʁE���H�E���p���A���W�Ɩ��ɂ��ẮA�n�敪�������܂߁A�����̎��Ǝ҂��Q���ł���悤�ɂ��� ���Ƃ��A�������̊m�ۂɂ��K���ȉ��i�ɂ��ϑ����\�ɂ��܂��B
�@�܂��A�I�ʁE���H�ɂ��Ă��A���݂̈ϑ��Ǝ҂��ߋ��ɂ����ł������悤�ɁA�s�����悵�Ď��Ǝ҂���Ă邽�߂̎x�����s�Ȃ��A���T�C�N�����i�Љ�̒S���� �Ƃ��Ă̎��Ǝ҂̌��S�Ȉ琬�ɗ͂𒍂��ׂ��ł��B
�i�T������j�@�@�܂����q�q
�u���̂��̊i���v�������ȁI
�@���{���Y�}����c���c���S���̕a�@�ɑ��čs�����A���P�[�g���ʂɏՌ����܂����B�S�V�s���{���̂V�Q�S�a�@���������A���ۗ����������A������ �N�ی��؎��グ�ɂ��d�lj����Ⴊ�V�Q�a�@�A�P�O�Q�V�����������Ƃ����̂ł��B�������̎��Ò��f�ɂ��]�o���A�ݒ�ᇂ��������A�ݐ��E�ɂ��ً}��p�A ���A�a���Â̒��f�ŏǏ����A���S��l�H���́A�̍d�ς̈����ŕ����A��p�̒x�ꓙ�̎��Ⴊ����܂����B
�@���Ô�̖��W�����R�W�V�a�@�łQ�Q���T�疜�~�ȏ�ɏ���Ă��܂��B�����������ʂ��A���r�W����ψ����́A�u�n���Ɗi�������̂��̊i���܂Ő��ݏo���� ����v�ƍ������܂����B
�@�����g���A�g�߂ȑ��k���Ⴉ��A���ۗ��ؔ[�ɂ���f�}���ɐS��ɂ߂Ă��܂������A���߂āA�u�����鍑�ۗ��ֈ����������I�v�ƌ��ӂ�V���ɂ��܂����B
�m �T������ �n
�������Ɗ��ۑS�@�@�Ȃ��܂ǂ�
�@����A�X����`�̈ړ����A�P�ʁA�P�ʑ��ŃA���~�ʂ��Ԃ��A���W�����Ă�����l�̘V�l���A���̎����Ă������Y�}�̂̂ڂ�������āA�삯����Ă����܂� ���B
�@�u�Ȃɂ��A�]��ł����������Ƃ����Ă���킯����Ȃ���ł��B�ł��A�ʏW�߂��ł��Ȃ��Ȃ�ΐ����ł��܂���B�v�܂𗬂��Ȃ���i���܂��B�������~�� �N����炵�B�A���~�ʂ̉���ʼn��Ƃ���炵���Ȃ��ł��������ł��B��������֎~��Ⴊ�c��ʼn����ꂽ���Ƃ������A�����ւ̑傫�ȕs��������Ă����� �����B
�@���{���Y�}�́A���̏��ɂ��āA�K�R�s���ɑ��A�������Ɗ��ۑS�s���̂ǂ��炪����{�I�Ȍ������Ǝ��^�Ŕ���܂����B�s���́u�������ł���v�Ɠ� �ق��܂����B��Ϗd�v�ȓ��ق��Ǝv���܂��B
�@�u�����������������Ă���v�Ƃ̎��_�����߁A�����������X���u���T�C�N���̋��͎ҁv�Ƃ��Č���̂Ȃ�A��������ۏႵ�Ȃ���A���ۑS�s���̐��i�� �}�邱�Ƃ͉\�ł��B�s�����ق̗���ł̋�̓I�Ȏ��g�݂����߂Ă��������Ǝv���܂��B